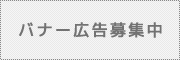- ペット記事
- 全国のペットな話題
- 九州のペットな話題
- 雑誌 犬吉猫吉
- 犬吉猫吉九州版とは
- 取り扱い主要書店一覧
- お散歩ウォッチング
- お散歩ウォッチングとは
- 参加特典のご案内
- 今後の開催スケジュール
- 午前中事前予約
- フォトランキング
わんちゃん部門 - 過去のランキング受賞者
- フォトランキング
にゃんちゃん部門 - 過去のランキング受賞者
- ポイント案内
- ポイントを貯める方法
- ポイントを使う方法
- 大切なお知らせ
- 犬吉猫吉サービス終了のご案内
犬の認知症リスクは1年ごとに1.5倍に、リスクに大きな差があった他の要素とは?
1万5000匹もの大規模調査、人間の認知症研究にも役立つ可能性
年老いた愛犬が突然、問題行動を起こしたり、迷子になったりすることはないだろうか。あるいは、長年一緒に暮らしてきた飼い主のことがわからなくなったような様子はないだろうか。
人間と同じように、イヌも年をとれば記憶力や認知能力が低下する。極端な例では「イヌの認知機能障害」(CCD)と言われるような状態になることもある。すると、睡眠パターンが乱れたり、空間認識能力が低下したり、社交性が変化したりといった症状も現れるようになる。
「人間が加齢によってかかる病気の多くは、イヌもかかります」。米ワシントン大学家庭医療学部の疫学者サラ・ヤーボロー氏は、電子メールでの取材にそう答える。「そういった病気がどのようにイヌに現れるのかについて理解が進めば、認知症のような(人間の)病気の進行の解明に役立つかもしれません」
ヤーボロー氏らは、CCDとイヌの基本的な特性との関連を詳しく調べるため、イヌの飼い主1万5000人以上から年齢、犬種のタイプ、活動レベルなどさまざまなデータを収集した。イヌ(Canis familiaris)にはティーカップ・チワワからグレート・デーンまで多様な犬種があり、それぞれで異なる大きさや体格、性格などの影響を解きほぐしつつ、各特性についてのCCDのリスクを評価した。
その結果、イヌがCCDになる確率は、1年ごとに1.52倍ずつ上昇していくことがわかった。
「不妊手術の有無、健康状態、犬種、活動レベルが同じであれば、1年先に生まれたイヌの方がCCDになるリスクは52%高くなります」とヤーボロー氏は説明する。氏を筆頭著者とする論文は、2022年8月25日付けで学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
さらに、飼い主が「活動的ではない」と申告したイヌは、CCDを発症している割合が6.47倍高かった。ただし、これは相関関係であって因果関係ではない。つまり、活動的でないことがCCDにつながるのか、CCDになったことで活動的でなくなるのかはわからない。この点については、さらに調査が必要だとヤーボロー氏は述べている。
「不妊手術の有無、健康状態、犬種、活動レベルが同じであれば、1年先に生まれたイヌの方がCCDになるリスクは52%高くなります」とヤーボロー氏は説明する。氏を筆頭著者とする論文は、2022年8月25日付けで学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
さらに、飼い主が「活動的ではない」と申告したイヌは、CCDを発症している割合が6.47倍高かった。ただし、これは相関関係であって因果関係ではない。つまり、活動的でないことがCCDにつながるのか、CCDになったことで活動的でなくなるのかはわからない。この点については、さらに調査が必要だとヤーボロー氏は述べている。
イヌの加齢に関する研究
加齢とCCDとの関連は、これまでも複数の研究で指摘されていたが、今回の研究はそれよりも規模がはるかに大きい。
獣医学の分野では100匹のイヌを対象とした研究でもかなり大規模と見なされることが多いと、米ノースカロライナ州立大学の臨床科学者で獣医師のナターシャ・オルビー氏は解説する。なお、氏は今回の研究に関与していない。
しかし、今回の研究では1万5000匹ものイヌのデータを使っている。このような調査が実現できたのは「ドッグ・エイジング・プロジェクト」(Dog Aging Project)によるところが大きい。2014年にケイト・クリービー、ダニエル・プロミスロー、マット・ケイバーラインの各氏によって設立され、米国立老化研究所などからの助成金を受けているプロジェクトだ。米国中の数万匹のイヌの情報を継続的に集めており、飼い主から獣医師の記録や生体サンプル(遺伝物質など)の提供を受ける場合もある。
一方でオルビー氏の研究室では、個々のイヌを複数の専門家が評価するという逆のアプローチから加齢に関する研究を行っているが、探し求めている答えはみな同じだ。
「こうした状況が優れている点は、アンケートで集めた実地での観察データを検証できることです。異なるグループ同士の研究に大きな相乗効果が現れています」とオルビー氏は述べている。
獣医学の分野では100匹のイヌを対象とした研究でもかなり大規模と見なされることが多いと、米ノースカロライナ州立大学の臨床科学者で獣医師のナターシャ・オルビー氏は解説する。なお、氏は今回の研究に関与していない。
しかし、今回の研究では1万5000匹ものイヌのデータを使っている。このような調査が実現できたのは「ドッグ・エイジング・プロジェクト」(Dog Aging Project)によるところが大きい。2014年にケイト・クリービー、ダニエル・プロミスロー、マット・ケイバーラインの各氏によって設立され、米国立老化研究所などからの助成金を受けているプロジェクトだ。米国中の数万匹のイヌの情報を継続的に集めており、飼い主から獣医師の記録や生体サンプル(遺伝物質など)の提供を受ける場合もある。
一方でオルビー氏の研究室では、個々のイヌを複数の専門家が評価するという逆のアプローチから加齢に関する研究を行っているが、探し求めている答えはみな同じだ。
「こうした状況が優れている点は、アンケートで集めた実地での観察データを検証できることです。異なるグループ同士の研究に大きな相乗効果が現れています」とオルビー氏は述べている。
CCDになる犬の割合と予防策
文=JASON BITTEL/訳=鈴木和博
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd2786bd2fa7b55bee44c2927779334680da758e?page=1
犬吉猫吉編集部2022.09.09
2023/12/27 



誠に勝手ながら、12/28(木)〜1/4(木)まで冬季休業期間とさせていただきます。…
2023/12/20いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 ポイン…
2023/12/15いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 現在ポ…
2023/12/06いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 現在ポ…
2023/12/04【対象の方:2023年12月3日のイベントにご参加いただいたゴールド会員様】 …
2023/12/04平素より、弊社会員サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 この度、ゴー…
2023/11/28いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 現在ポ…
2023/11/22いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 現在ポ…
2023/11/10いつも犬吉猫吉会員サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 現在ポ…
2023/11/06Copyright(c) INUKICHI-NEKOKICHI NETWORK, ALL Rights Resrved.